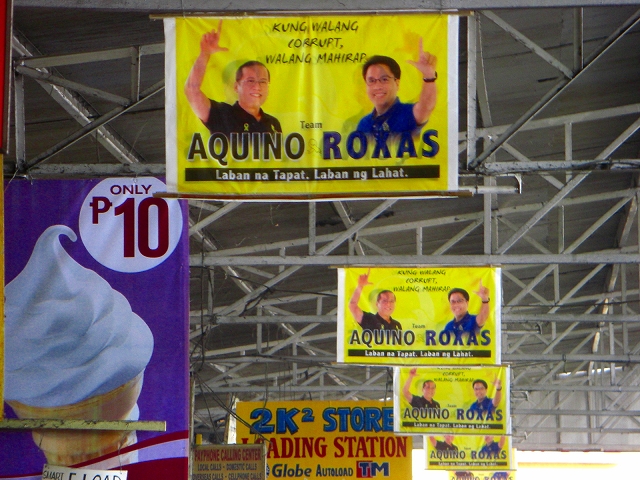パスコの相棒のジェーンに赤ちゃんが生まれた。34歳の高齢初産の上、臨月になって赤ん坊の体重が9ポンド(4kg)もあると医者に告げられ、難産が危惧されたが、帝王切開で3月31日、無事に男の子を出産した。 マンダルヨン市、ボニーの中規模の病院で出産したが、早速お見舞いに行くとたくさんの生まれたての赤ちゃんが並んでいた。どれもこれも同じ顔をして区別がつかないが、ガラス越しに連れてきてもらうと確かに大きな赤ちゃんで、髪も黒々としていた。お父さんのカーネル(大佐)は昨夜の入院以来一睡もしないで、つきそっていたとのこと。また、写真におさめた分娩の様子を見せてもらったが、最近は父親が分娩に立ち会うのがトレンドのようだ。 翌日私はホリーウイークを利用して息子と一緒にルソン島北部(バギオ、イロコス)の旅に出たが、7日に戻ってくる丁度その日に母子が退院した。フィリピンでは分娩後通常2日ほどしか病院にいないが、帝王切開のため、1週間以上入院していたことになる。帝王切開の上、1週間も入院していたため、病院からびっくりするような請求書が来て一同頭を痛めていたが。 国家警察の幹部と言う重職にありながら、カーネルは入院以来一週間パタニティー・リーブを取って、つきっきりで赤ん坊と母親の面倒を見ている。メイドもいるのだが人には任せてはおれない、といったところだろう。夜中も泣き止まない赤ん坊を抱いて育児に専念しており、仕事どころではないようだ。私が子育てをしていたころはパタニティ・リーブなどという概念は無くて、合計たったの3日間の有給休暇だけで、余分な年休をとると上司にいやみさえ言われたことを思い出す。 本文とは関係ないが、家の近くにある木が満開の黄色い花を咲かしていた。花の形は藤の様でもあるが、日本では丁度桜の季節なのでお花見の気分を味わうことが出来た。